はじめに:薬の飲み合わせは意外と身近なリスク
薬を飲むとき、つい見落としがちなのが「飲み合わせ」。
市販薬は比較的安全に使えるよう設計されていますが、複数の薬を同時に使うときは注意が必要です。特に子育て中のご家庭では、家族みんなの市販薬やサプリメントを用意していることも多く、思わぬリスクが潜んでいる場合も。
この記事では、登録販売者の視点から、身近な「薬の飲み合わせリスク」と安全に使うためのポイントを解説します。
飲み合わせで注意が必要な代表例
① 解熱鎮痛剤と風邪薬
風邪薬の多くには解熱鎮痛成分(アセトアミノフェンやイブプロフェンなど)がすでに含まれています。
そこに、さらに市販の解熱鎮痛剤を追加で飲むと、成分の重複により肝臓や腎臓に負担をかけるリスクがあります。特にアセトアミノフェンは過剰摂取すると肝障害を起こす可能性があるため注意が必要です。
② 抗ヒスタミン薬と眠気を引き起こす薬
花粉症薬や風邪薬に含まれる「抗ヒスタミン薬」は眠気を引き起こします。
そこに睡眠導入剤やお酒が加わると、眠気や集中力低下が強まり、思わぬ事故や転倒につながることもあります。車の運転や機械作業をする際は特に注意が必要です。
③ 胃薬と鉄剤・カルシウム製剤
胃薬の中には、胃酸を抑える作用のある「制酸剤」があります。
制酸剤を飲んでいると鉄剤やカルシウム製剤の吸収が妨げられることがあり、貧血の治療や骨粗しょう症予防の効果が十分に得られないケースも考えられます。
④ サプリメントとの飲み合わせ
健康のためにサプリメントを飲む方も多いですが、これも注意が必要です。
たとえば、ビタミンKを含むサプリは、血液をサラサラにする薬(ワーファリンなど)の効果を弱めてしまうことがあります。
「市販薬+サプリメント」という組み合わせも油断せず確認しましょう。
子ども・高齢者の飲み合わせは特に注意
子どもや高齢者は代謝機能が弱かったり、体重あたりの薬の影響が大きかったりします。
例えば:
- 子ども
風邪薬や解熱鎮痛剤は年齢・体重に応じた用量を守らないと危険です。複数の市販薬を併用する際は、同じ成分が重複しないよう注意が必要です。 - 高齢者
血圧、糖尿病、心臓病などの治療薬を服用している方が多く、市販薬の影響で副作用が強まる場合があります。
市販薬を安全に使うためのポイント
- 自己判断で複数の薬を併用しない
- 服用中の薬はメモやお薬手帳にまとめる
- サプリメントも含めて情報共有する
- わからないときは登録販売者・薬剤師に相談する
市販薬は手軽に使える反面、飲み合わせに関してはプロのアドバイスが非常に役立ちます。
まとめ:わからない時は薬剤師・登録販売者に相談を
薬の飲み合わせは、普段意識していなくても意外と身近に起こり得ます。
市販薬も使い方次第ではリスクにつながるため、自己判断せず、登録販売者や薬剤師にぜひ相談してください。
ご家族の健康を守るために、少しの注意と知識が大切です。

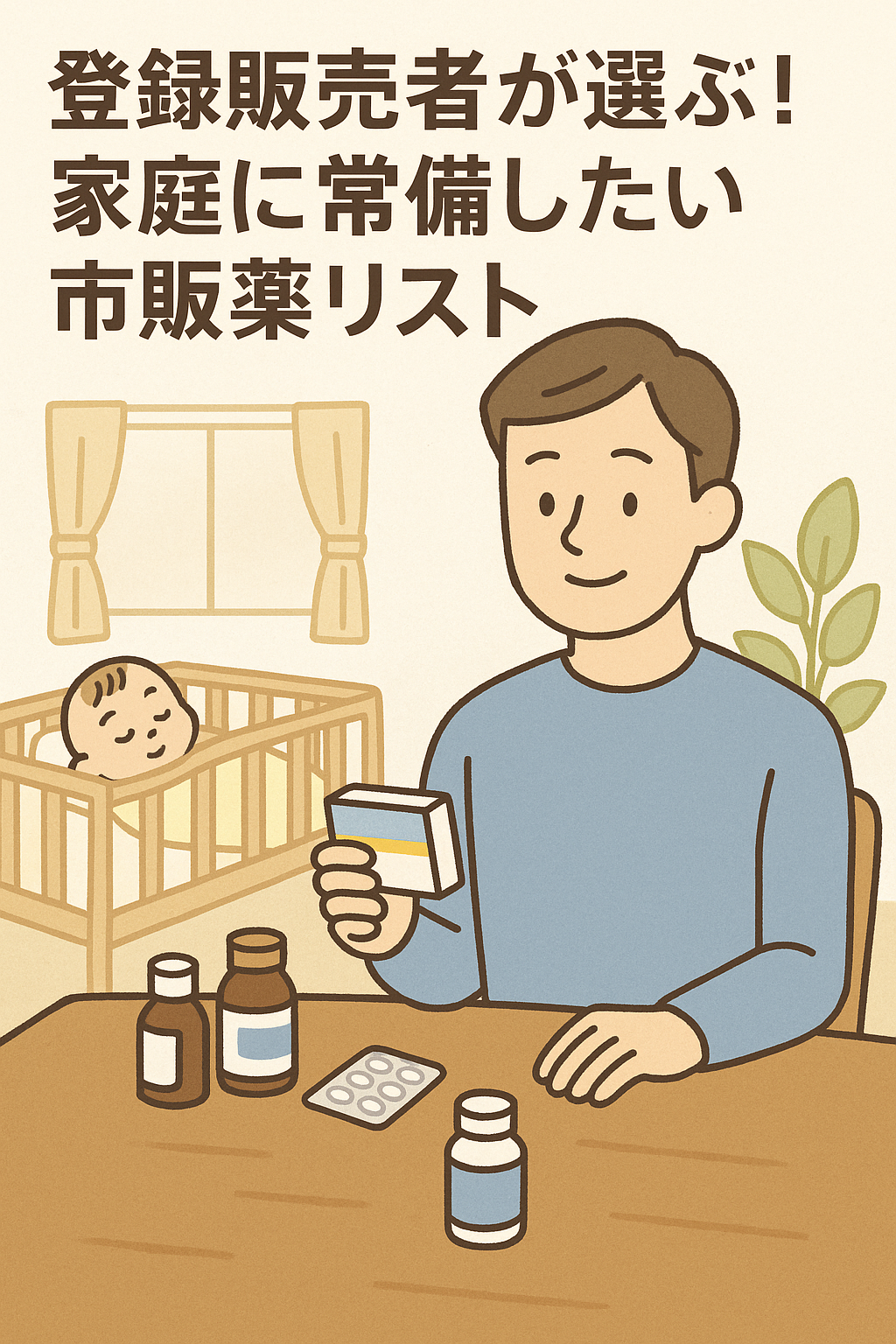


コメント