はじめに
ドラッグストアに行くと、同じようなパッケージの薬がずらりと並んでいます。
「これってメーカーが違うだけで中身は同じなの?」「それとも成分も違うの?」と迷ったことはありませんか?
実は――
市販薬には“同じ成分のもの”もあれば、“配合が違うもの”もあります。
この記事では登録販売者の視点から、市販薬の違いと成分の見分け方を解説します。
市販薬の違いは大きく3つ
1. 成分は同じでメーカーが違う薬
- いわゆる「ジェネリック的な存在」です。
- 主成分は同じでも、メーカーごとに名前やデザインが違います。
- 例:イブプロフェンを主成分とした「イブA錠」と、同じイブプロフェンを使った他社製品。
👉 成分は同じでも「添加物」や「剤形(錠剤・顆粒など)」に違いがあることがあります。
2. 配合成分が異なる薬
- 同じ「風邪薬」でも、中身は違います。
- 鼻水に強いタイプ、咳に強いタイプ、熱や頭痛に強いタイプなど、症状に合わせて配合を工夫しています。
- 鎮痛薬も種類があり、代表的なものは:
- イブプロフェン型(炎症や痛みに強い)
- ロキソプロフェン型(即効性がある)
- アセトアミノフェン型(子どもや高齢者でも使いやすい)
👉 名前が似ていても、中身は大きく違うことがあります。
3. 剤形や添加物の違い
- 剤形:錠剤・顆粒・液体・ドリンクタイプなど。飲みやすさが違います。
- 添加物:眠気を抑える成分、胃を保護する成分など、メーカー独自の工夫が加えられることもあります。
👉 例えば「胃にやさしいタイプ」「眠くなりにくいタイプ」はこの工夫の結果です。
成分の見分け方
- パッケージ裏の「成分・分量」欄を必ずチェックしましょう。
- 主成分が同じなら効き目も似ています。
- 効能・効果の欄を見れば「鼻水用」「咳止め」「解熱鎮痛」など対象が分かります。
登録販売者からのアドバイス
- 見た目が似ていても「成分や配合」が違う場合が多いです。
- 「どこに効かせたい薬か」を確認すれば選びやすくなります。
- 迷ったときは症状を伝えて、薬剤師や登録販売者に選んでもらうのが一番安心です。
くすりちゃんとしずくちゃんの会話 💬
💊くすりちゃん:「薬って、名前が違うだけで中身は同じなんじゃないの?」
🩺しずくちゃん:「同じ成分の薬もあるけど、症状に合わせて配合が違うことが多いんだよ!」
💊くすりちゃん:「なるほど〜。成分表を見れば違いがわかるんだね!」
まとめ
- 市販薬は「メーカーが違うだけ」の場合もあれば「成分が違う」場合もある
- 成分表を見れば違いが分かりやすい
- 自分の症状に合った薬を選ぶことが大切
👉 関連記事
📢 最新情報はXでも発信しています👇
👉 副業パパ@登録販売者パパのXアカウント



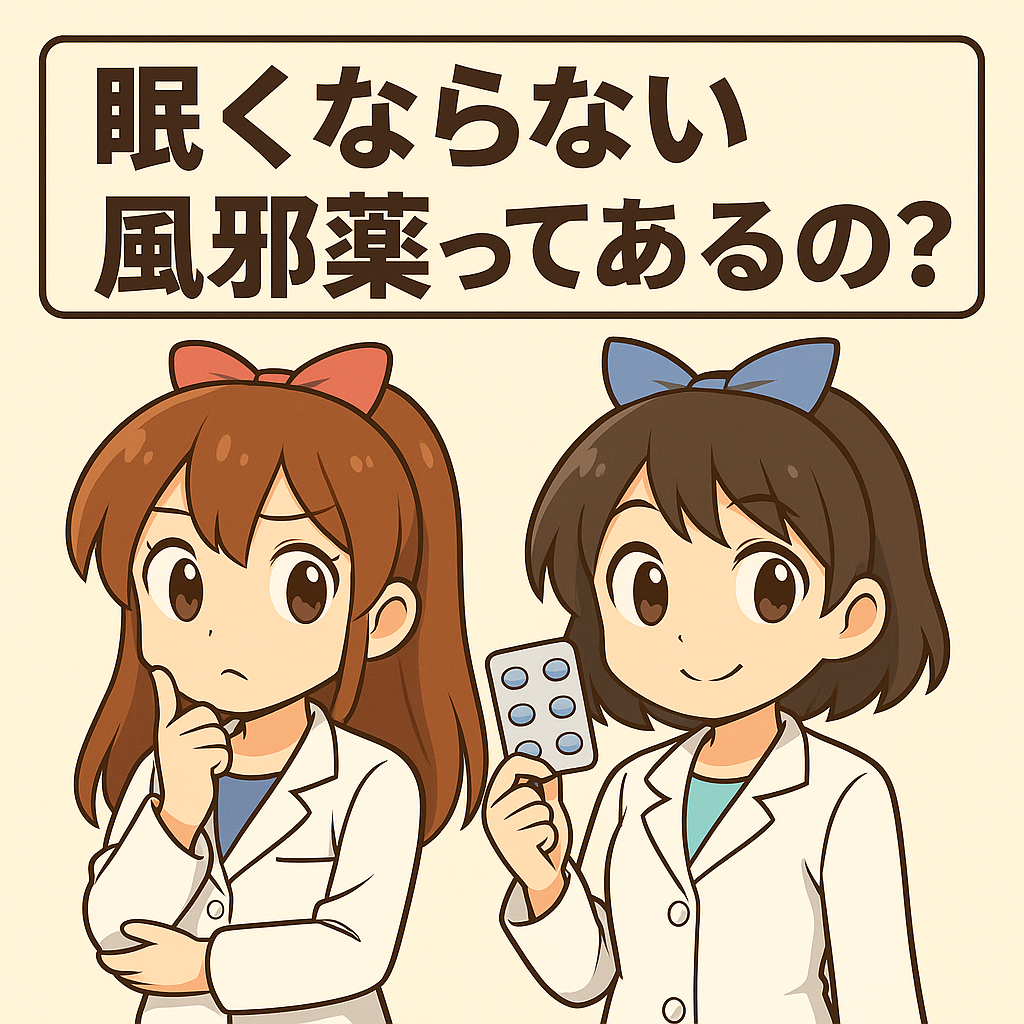
コメント