はじめに|「第1類?第2類?なんだか難しそう…」
薬局で市販薬を選んでいると、パッケージに書かれている
「第1類医薬品」「指定第2類医薬品」などの表記を見て、
「これってどういう意味?」と戸惑ったことはありませんか?
実はこの“分類”には、薬の強さ・リスク・相談の必要性が関係しています。
登録販売者として、日々この分類を意識しながら販売している立場から、
わかりやすく解説していきます。
市販薬は「リスクの高さ」で分類されている
市販薬(一般用医薬品)は、副作用などのリスクの大きさによって
大きく3つに分類されています。
| 分類 | 相談の必要性 | 主な購入方法 | 例 |
|---|---|---|---|
| 第1類医薬品 | 薬剤師の説明が必要 | 店頭またはネットで購入(薬剤師の確認あり) | 一部の目薬、スイッチOTC薬 など |
| 第2類医薬品 | 登録販売者の説明が望ましい | 店頭・ネット購入可能 | 解熱鎮痛薬、風邪薬など一般的な薬 |
| 第3類医薬品 | 比較的リスクが低い | 店頭・ネット購入可能 | ビタミン剤、整腸薬など |
💡「指定第2類医薬品」って何?
第2類の中でも、特に注意が必要とされている成分を含む薬に付けられる表示です。
→ 登録販売者の積極的な声かけ・確認が推奨されます。
- 例:ロキソプロフェン(ロキソニン系)、イブプロフェン など
なぜこの分類が大事なの?
分類が異なることで、
- 🔸 どこで買えるか(ネット・店頭)
- 🔸 誰から説明が必要か(薬剤師・登録販売者)
- 🔸 どの程度のリスクがあるか
がすべて変わってきます。
例えば、第1類医薬品は薬剤師がいないと販売できません。
第2類や第3類は、登録販売者が対応可能ですが、症状や状態によっては販売を見送ることもあります。
自分で薬を選ぶときに気をつけるポイント
✅ 1. 分類は「効果の強さ」ではなく「リスクの大きさ」
「第1類だからよく効く」というわけではなく、
副作用リスクや使用時の注意点が多い薬が第1類に分類されます。
✅ 2. 指定第2類は「要注意」サイン
妊娠中・高齢者・他の薬を使用中の方は、
指定第2類の薬でも体調に影響する可能性があるため、
購入前に必ず相談するのが安心です。
✅ 3. ネットで買える薬でも、しっかり成分と分類を確認
市販薬のネット購入が一般的になっていますが、
「分類」と「使用上の注意」をしっかり読まないと、
思わぬトラブルになることもあります。
よくある質問(Q&A)
Q. 「指定第2類」と「第2類」の違いは?
→ 「指定第2類」は第2類の中でもよりリスクが高い成分を含みます。
店頭では登録販売者の説明や注意喚起が必要です。
Q. 薬剤師がいないドラッグストアでも薬は買える?
→ 第2類・第3類医薬品であれば、登録販売者がいれば販売可能です。
ただし、第1類医薬品は薬剤師がいないと販売できません。
Q. 小さい子どもに使える薬はどの分類?
→ 分類ではなく成分・年齢制限を確認することが大切です。
「〇歳以上使用可」などが記載されているので、そちらを優先しましょう。
あわせて読みたい関連記事
まとめ|分類を知って、安全に薬を選ぼう
- 市販薬は「リスクの高さ」で第1〜第3類に分類されている
- 指定第2類はとくに注意が必要な薬のサイン
- 自分に合った薬を選ぶには、分類+症状+使用環境を総合的にチェック
- 不安があれば、登録販売者に気軽に相談を!


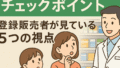

コメント